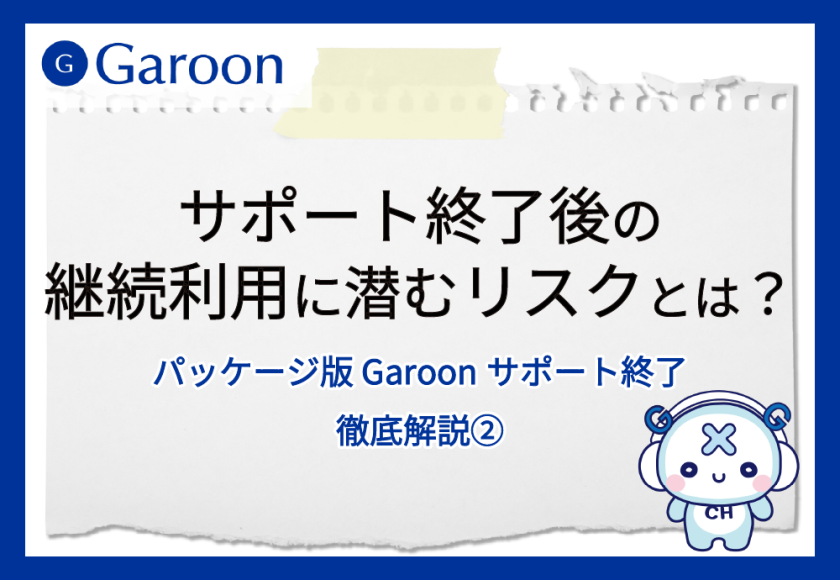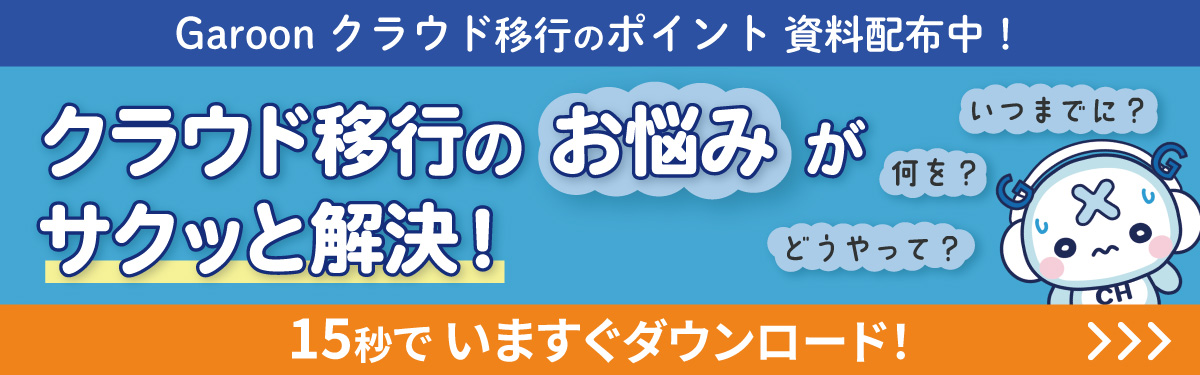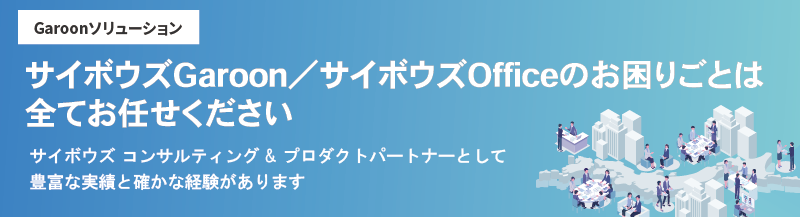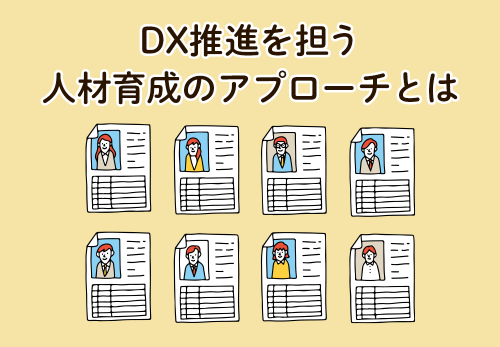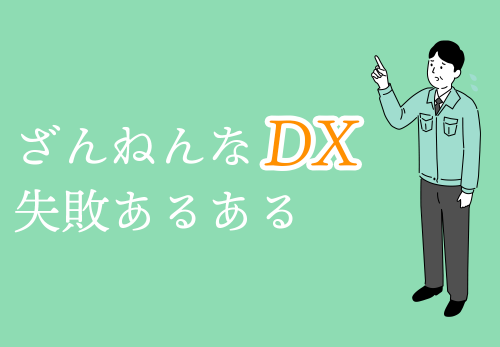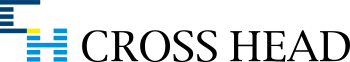目次
著者:小島真鈴 文系出身のkintoneエンジニア。
2020年新卒入社以来、業務理解力を武器に、顧客に寄り添ったシステムの提案と構築を行う。 kintoneカイゼンマネジメントエキスパートおよびSC-Garoon資格を保持し、「kintoneのことならなんでもおまかせ!」はもちろん、「Garoonのこともおまかせ!」な頼れる存在。 趣味はアイドルのライブ参戦と、最近は「ようとん場」というゲームに夢中。 |
第1回:サポート終了の概要と今後の選択肢
第2回:サポート終了後の継続利用に潜むリスクとは? ←閲覧中の記事
第3回:知っておきたい!クラウド版の特徴とメリット
第4回:クラウド移行の費用とスケジュール
第5回:よくある失敗と成功のヒント※事例あり
はじめに
前回の記事では、「パッケージ版 Garoonのサポート終了 徹底解説」の第1回として、サポート終了の概要や今後の選択肢を整理しました。
サポート終了までには数年の猶予があります。そのため、多くの方が「今すぐ対応しなくても大丈夫」「しばらくは使える」と思うのではないでしょうか。
実際、サポート終了後やライセンスが切れた状態でも利用できる製品は多く、期限直前や期限を迎えたタイミングでバージョンアップやライセンス更新を検討するケースも少なくありません。
しかし、サポート終了製品の利用を継続することで、予期せぬ不具合や業務への深刻な影響が生じる可能性も否定できません。
今回は、「パッケージ版 Garoonのサポート終了 徹底解説」の第2回として、サポート終了後に起こり得るリスクや、対応策を取らずに放置した場合に懸念されるトラブルについて、事例を交えながらご紹介します。
サポート終了で何が起こる?

製品のサポートが終了しても、利用は継続できる場合があるため、「まだ使えるから問題ない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、サポート終了製品には、見過ごされがちなリスクが潜んでいる可能性があります。
特に、セキュリティや運用面での問題が徐々に顕在化し、時には業務に支障をきたすケースも考えられるでしょう。
この章では、サポート終了に伴って起こり得る主なリスクについて、3つの観点から整理します。
セキュリティ対応不可による企業信用への影響
製品のサポートが終了すると、バージョンアップが提供されなくなります。
バージョンアップには、機能追加や改善だけでなく、OSやブラウザーのアップデートへの対応や脆弱性(ぜい弱性:攻撃者に悪用される可能性のあるセキュリティ上の弱点や欠陥)への対応も含まれます。
そのため、仮に製品に深刻な脆弱性が発見されたとしても、多くのメーカーでは製品の修正バージョンを提供しないことがほとんどです。
このような状態が続くと、外部からの脆弱性を利用した攻撃リスクが日に日に高まり、情報漏洩やシステム停止といった重大な事態につながる可能性も否定できません。
特にGaroonは、社内のスケジュール管理やワークフロー、掲示板など、日々の業務に密接に関わる情報を扱うシステムです。
顧客情報や取引情報など、企業にとって重要な情報を含む可能性も高いでしょう。
万が一、脆弱性が発見され不正アクセスを受けた場合、社内での業務の混乱を招くだけではなく、社外からの社会的信用にも深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
不具合への対応不可による業務影響
サポート終了製品では、OSやブラウザーのアップデートに伴って、画面の表示崩れや動作不良が発生するケースもあるようです。
たとえば、社内で利用している特定のブラウザーでGaroonの画面が正しく表示されなくなることや、入力操作に不具合が生じる可能性も考えられます。
予期しないトラブルが発生した際に、サポート中の製品であれば修正バージョンが提供され、問題を速やかに解決できることでしょう。
しかし、サポート終了後は不具合に対する修正バージョンが提供されないため、利用者自身が可能な範囲で対応するしかありません。
場合によっては一部機能の利用を断念せざるを得ない状況も想定されます。
Garoonは、職種や役職を問わず多くの社員が日常的に利用しているシステムです。
そのため、不具合によって利用頻度の高い機能がまったく使えなくなった場合、著しい生産性の低下や社内混乱につながる可能性があります。
日常的な業務に影響が出る前に、トラブルが発生した際の対応方針を検討しておくことが望ましいといえるでしょう。
公式サポート終了による課題対応の困難化
メーカーによるサポートが終了するタイミングで、一般的には製品を取り扱うベンダー(製品の販売や導入の支援をする企業)からのサポートも停止されます。
そのため、トラブルが発生した際に、メーカーやベンダーから技術的な支援を受けることができなくなります。
結果として、社内での無理な問題解決が求められ、特定の担当者に運用が依存する「属人化」が進むケースも見受けられます。
このようなケースでは新たな課題として、Garoonの設定を担当していた社員が異動や退職した場合、ノウハウの継承がうまくいかず、トラブル対応に時間がかかることも考えられます。
さらに、発生した問題に対してメーカーやベンダーによる調査・対応が期待できないため、社内リソースだけで解決しなければならない状況に陥ることもあるでしょう。
このように、サポートの終了によって、トラブル対応が困難になる可能性があり、社内での運用負荷が高まる懸念もあります。
製品のバージョンアップや後継製品へのリプレースが行われず、放置された環境では、こうしたリスクが徐々に顕在化し、業務に支障をきたすケースも報告されています。
次の章では、トラブル事例をもとに、サポート終了製品を放置することでどのような影響が生じるのかをご紹介します。
放置リスクとトラブル事例

サポート終了に伴うリスクを認識していても、「今すぐ困るわけではない」と判断し、対応を先送りにしてしまうケースもあるかもしれません。
製品利用時のトラブルは頻繁に発生するものではないかもしれませんが、ある日突然トラブルが発生し、業務に深刻な影響を及ぼしたという報告も見受けられます。
この章では、製品のサポート終了後も利用を継続したことで発生した、具体的なトラブル事例をご紹介します。
事例を通じて、サポート終了製品を放置することによる影響の大きさや、事前対応の重要性について考えていきましょう。
事例①:予定表が表示されなくなり混乱が生じた
ある企業では、ブラウザーのアップデート後に製品の画面が崩れてしまい、スケジュールが正常に表示されなくなるという不具合が発生しました。
予定表が正しく表示されないことで、予定の確認や登録ができず、社内業務に大きな混乱が生じました。
一時的な措置として、紙やExcelベースでのスケジュール管理に切り替えざるを得ず、業務効率は大幅に低下したといいます。
このような不具合は、製品が最新のブラウザー仕様に対応していないことが原因と考えられます。
一般的なソフトウェアのメーカーでは、OSやブラウザーのアップデートの影響を可能な限り受けないよう事前に検証と対応を行いますが、サポートが終了した製品ではこうした対応が行われません。
事例②:情報漏洩の懸念が生じた
製品に脆弱性が存在していたにもかかわらず、サポート終了により修正バージョンが提供されない状況が続いていました。
その結果、掲示板に投稿された社内情報が外部から閲覧可能になっていたことが判明した事例もあります。
社内では緊急対応に多くの時間を取られたうえ、情報管理体制の見直しを迫られる事態となりました。
このようなセキュリティインシデント(事故)は、サポート終了製品を利用し続ける環境を放置することで発生するリスクの一例といえるでしょう。
脆弱性への対応ができない環境では、情報漏洩や外部からの不正アクセスといった重大な問題につながる可能性があります。
事例③:障害対応に不安が残った
製品の動作が不安定になった際、メーカーやベンダーのサポートが受けられず、社内での原因調査と復旧に多くの時間と人手を要したケースも報告されています。
特に原因調査においては、公式の最新情報が得られない中で対応を迫られたため、IT部門の負担が大きくなったといいます。
また、復旧には至ったものの、社内の人員だけで判断した対応が恒久的に問題のないものかどうか、不安が残る結果となりました。
サポート終了後は、障害対応に関する情報や支援が得られなくなるため、社内だけでの対応には限界を感じる場面も出てくるかもしれません。
これら3つの事例を踏まえると、サポート終了製品を放置することが、日常業務や企業の信用に深刻な影響を及ぼす可能性があることがわかります。
安定した運用を維持するためには、サポート期限が近づく前に、適切なバージョンアップや製品の切り替えについて検討を開始するなど、早期の対応が必要となってくるでしょう。
では、企業としてどのような対応を検討すべきでしょうか。
次の章では、今後の選択肢や移行に向けたポイントについて整理します。
企業が今すぐ検討すべきこと

サポート終了を前に、企業としてどのような準備を進めておくべきか、具体的なステップに悩まれている方も多いのではないでしょうか。
この章では、クラウド版 Garoonへの移行を含め、企業が検討すべき対応ポイントを整理します。
クラウド版 Garoonへの移行
前回の記事で紹介した通り、クラウド版 Garoonへの移行は、サイボウズ社が推奨する対応方法となります。
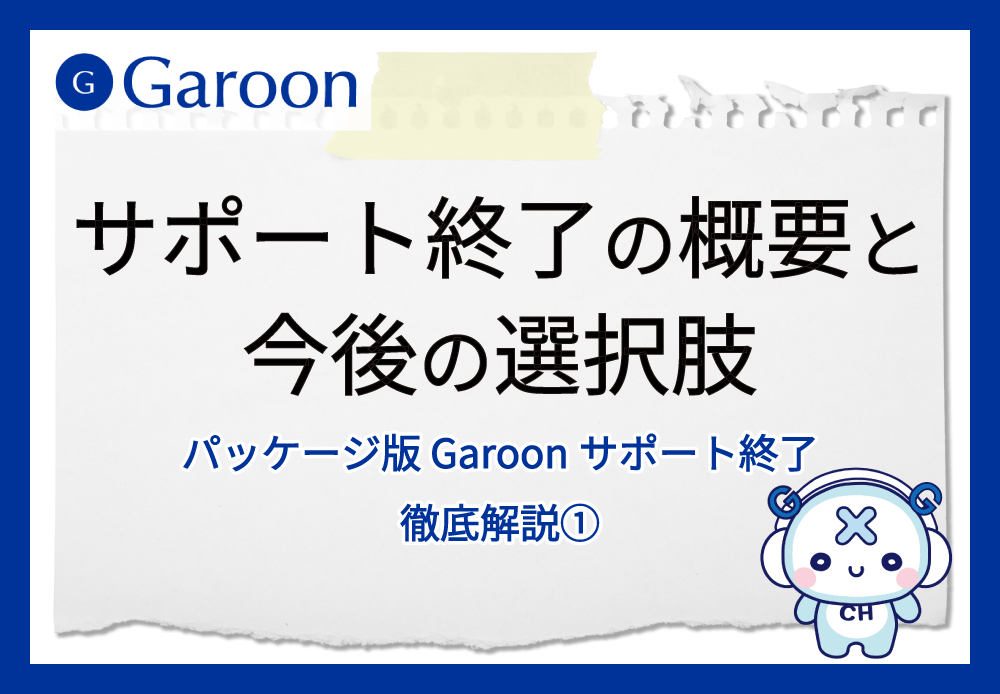
クラウド版 Garoonでは、常に最新の機能やセキュリティアップデートが提供されるほか、利用者側でのサーバー管理や保守作業の負担が解消されるため、安定した運用と生産性の向上を両立できる選択肢とされています。
また、操作性はパッケージ版 Garoonとほぼ同じであるため、ユーザー教育もほとんど不要で比較的スムーズな移行が期待されます。
ただし、部分的に提供されない機能もあるため、移行にあたっては現在の利用状況や必要な機能を整理し、クラウド版での運用に支障がないかを事前に確認することが重要といえるでしょう。
移行スケジュールの策定と社内調整
クラウド版 Garoonへの移行を進める際には、スケジュールの策定と社内での調整が重要なステップとなります。
まずは、現在のパッケージ版 Garoonの利用状況を把握し、どの機能やデータを移行対象とするかを整理することが求められるでしょう。
業務への影響を最小限に抑えるためには、段階的な移行の検討や繁忙期を避けた移行タイミングの選定なども重要なポイントです。
また、関係部門との連携や利用者への周知・研修なども含めた社内調整も、スムーズな移行には欠かせません。
こうした準備を早期から進めることで、移行後の混乱を防ぎ、スムーズな運用につなげることが期待されます。
パートナー企業に相談
クラウド版 Garoonへの移行や運用に少しでも不安を感じる場合は、自社だけでの解決を試みるのではなく、サイボウズ社認定のオフィシャルパートナー企業に相談することをおすすめします。
移行に関する知見や実績を持つパートナー企業であれば、現行環境の調査・整理から移行計画の立案、クラウド版 Garoonでの運用支援まで幅広くサポートを受けることができるでしょう。
また、パートナー企業からの支援は単なる移行支援にとどまらず、業務改善や他システムとの連携など、今後の活用を見据えた提案を受けられるケースもあります。
自社だけでの対応が難しいと感じた場合は、移行支援を提供しているパートナー企業に相談することでスムーズな移行が期待できるでしょう。
移行の検討は、業務への影響を最小限に抑えるためにも、早めに着手しておくことが望ましいと考えられます。
いつでも相談や検討を開始できるように、まずは利用状況の整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
最後に
今回は、パッケージ版 Garoonのサポート終了に伴う、”リスクやトラブル事例、企業が検討すべき対応”について、整理しました。
今後の対応方針を検討する際の参考になれば幸いです。
次回「【パッケージ版 Garoonサポート終了 徹底解説③】知っておきたい!クラウド版の特徴とメリット」では、クラウド版Garoon移行を進める際に役立つ「具体的なスケジュールの立て方やコストの見通し、移行時の注意点」などを詳しくご紹介します。
ぜひご覧ください!
第1回:サポート終了の概要と今後の選択肢
第2回:サポート終了後の継続利用に潜むリスクとは? ←閲覧中の記事
第3回:知っておきたい!クラウド版の特徴とメリット
第4回:クラウド移行の費用とスケジュール
第5回:よくある失敗と成功のヒント※事例あり
クロス・ヘッドはサイボウズ社のコンサルティング&プロダクトパートナーです。
クロス・ヘッドは、サイボウズ社認定のオフィシャルパートナーとして認定されており、2005年以来のサイボウズ社製品の取り扱い実績を有しています。また、サイボウズが設定しているパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report」にてインテグレーション部門2つ星を4年連続受賞。豊富な実績をもとに、様々なお客様ニーズにお応えします。弊社以外で導入されたお客様へのサービス提供も可能です。
※クロス・ヘッドはサイボウズ社のオフィシャルパートナーです。