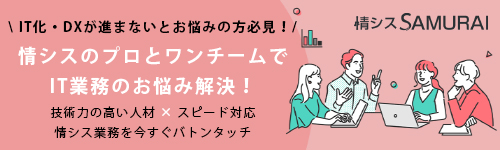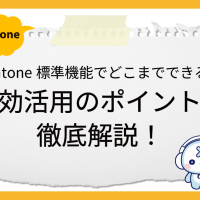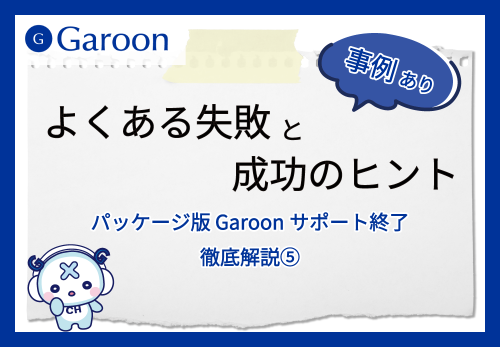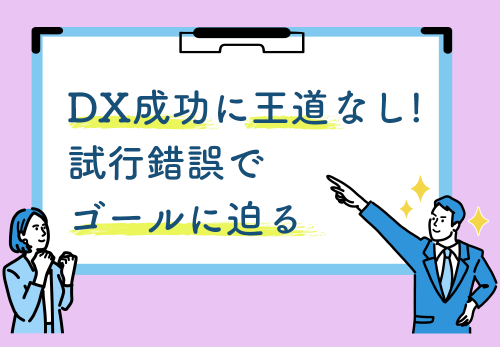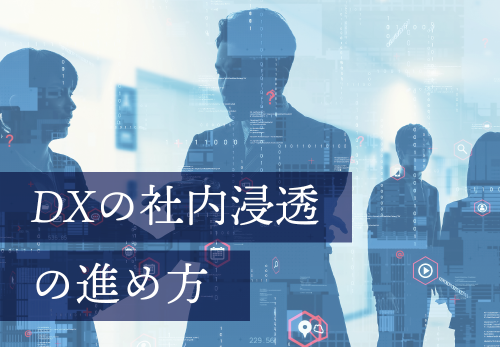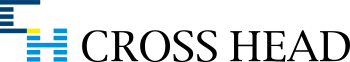中堅・中小企業を中心に、情報システム業務をひとり、あるいは少人数で担う「一人情シス」というキーワードを聞いたことはありますか?
近年、経営の合理化が求められる一方で、ITインフラの複雑化とDX推進の加速により、情シス関連業務の重要性が増しています。限られたリソースで幅広い業務を支える「一人情シス」体制は、企業にとってリスクになり得ます。
本ガイドでは、「一人情シス」の定義や発生背景をはじめ、実情と直面する課題、さらに環境改善の成功事例までを多角的に解説します。社内IT管理の属人化や人材不足に悩む情シス担当者にとって、実務に直結するヒントとなれば幸いです。
目次
一人情シスとは?増えている背景と現状

かつての情報システム部門は複数名体制が当たり前でしたが、今や「一人情シス」という働き方の実情があります。本業のコア業務へ集中するために情シス関連業務を外部へ委託(アウトソース)する企業も少なくありません。本章では、そのような状況が生まれている背景と、現場で実際に起きている変化について詳しく見ていきます。
情シス部門の縮小と業務の属人化が進む現実
「一人情シス」とは、情報システム部門の業務を実質的に1人で担当している状況を指します。このキーワードが広く知られるようになった背景の1つに、2017年に「伝説の一人情シス」として知られる黒田光洋氏が日経XTECHで連載した「10人のIT部門が消滅~一人情シス顛末記」があります。
現在、情シス部門をコスト削減の観点から縮小する傾向も多く、業務のIT化は加速度的に進んでいます。クラウドサービスの普及、テレワークの拡大、DX推進など、企業のIT依存度は年々高まる中で、変化に対応できる専門人材の確保が難しい状況が続いています。
多様化する「一人情シス」の働き方
一人情シスの働き方は多様で、総務や経理などの本業と兼務する「兼任型」が一般的です。特に規模の小さい企業やIT関連以外の業種、スタートアップ企業において、専任でIT業務に従事する人は少ないのではないでしょうか。
IT経験が少ない「ジュニア一人情シス」がいる企業も珍しくなく、経歴もさまざまな背景の人が見られます。「PCに詳しい」という理由のみで管理職が兼務、あるいは総務・管理部門の延長や社長命令によるデジタル化推進担当など、多岐に渡ります。
【3分でチェック】あなたの会社は「一人情シス」?セルフ診断
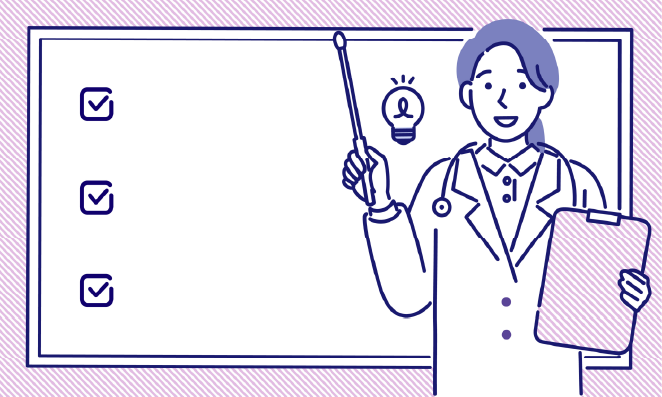
自分の会社が「一人情シス」の状況にあるかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
IT業務をほぼ1人で対応している
システム管理からユーザーサポートまで幅広い業務を、実質的に1人ですべて対応。代替要員が社内におらず、不在時の業務継続性に課題がある。
システム導入からパソコン設定まで全て自分
導入機器の選定や購入、初期設定、運用までのすべての工程を1人で担当している。また、外部ベンダーの選定や導入判断も、自身の裁量で進めざるを得ない状況。
トラブル時の対応が属人化しており、代替要員がいない
システム障害やトラブルの発生時に社内に頼れる人材がいないため、すべての対応が属人化している。休暇中でも緊急の連絡が入るため、十分な休息が取れない。
担当はしているが肩書きは「経理」「総務」
情報システム関連の業務を日常的に担当しているが、正式な情シス部門や役職は与えられておらず、「経理」や「総務」といった別の肩書きで業務を兼任している状態。
社内のIT知識が一部の人に偏っている
社内におけるIT関連知識やノウハウが一部の担当者に集中して、全社的なIT活用や効率化も進みにくく、組織全体の生産性や柔軟性に課題を抱えている状況。
これらの項目の3つ以上に当てはまる場合は、あなたの会社は「一人情シスの課題」を抱えているかもしれません。
一人情シスを取り巻くリアルな課題と解決策

一人情シスは社内ITの重要な役割を担っていますが、多くの課題と見過ごされがちな苦悩が潜んでいます。個人の負担にとどまらず、一人情シスという体制そのものが、企業全体にとっても運営リスクや組織構造的な課題となっていることも少なくありません。
ここでは具体的な課題と克服するための解決策を見ていきましょう。
業務範囲の広さへの対応
一人情シスが直面する最大の課題は、担当する業務範囲の広さです。
技術領域だけでも、サーバー・ネットワーク管理、セキュリティ対策、システム開発・保守、クラウド管理など、それぞれが専門性の高い分野です。これらの技術は日進月歩で進化しており、最新の知識を維持するだけでも相当な時間と労力が必要です。普段からの社内利用者のPC設定・トラブル対応、ソフトウェアインストール、操作指導・研修など、教育者や相談相手としての役割も求められます。
さらに経営・企画領域では、IT投資計画策定、ベンダー選定と交渉、セキュリティポリシー策定、DX推進企画など、経営戦略に直結する重要な判断を求められる可能性があります。
解決のためには業務の優先度を明確化し、より重要な業務に集中する環境を作ることです。また、業務の一部は外部へ委託することで負担を軽減することが可能です。
業務継続リスクの軽減
一人情シス体制であっても、システムトラブルや緊急対応の際には迅速な対応が必要です。障害対応が遅れることでシステム停止時間が長期化し、業務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。とくに、24時間365日稼働が求められる業務システムでは、担当者にかかるプレッシャーが非常に大きく、「一人情シス」最大の課題といえるでしょう。
常に緊急連絡用の携帯電話を手放せない、休暇中でも気が休まらないなど、業務時間外の拘束感も強く、心理的安全性の確保や健康への配慮が課題となります。こうした状況は、人材流出や離職リスクの高まりにもつながり、結果的に企業としての業務継続性にも影響を及ぼします。
これらの属人化による業務継続リスクを軽減するために、社内のナレッジ(知識)の共有化やドキュメント化の整備が重要です。業務手順やトラブル対応時のマニュアルを整備して、他のメンバーがサポートできる体制を構築していきましょう。
担当者の孤立と属人化した判断
一人情シス担当者の中には、社内にITの相談相手がいない孤立感に悩みながら、業務に取り組むケースも少なくありません。IT関連の知見を共有できる人材が不足していることで、技術的なディスカッションが困難で、判断を一人で背負い込む状態が続きます。
結果、重要なシステム選定や導入判断、トラブル対応において、誤った判断をしてしまうリスクが高まります。
孤立感の解消には、社内外のネットワークに参加、活用することが効果的でしょう。ユーザーコミュニティや外部のパートナーとの連携を強化し、情報交換や技術的なサポートを受けられる場をつくることで、精神的な負担を軽減できます。
他社はどうしている?企業側が改善する一人情シスのリアル事例3選

企業はこの状況をどう乗り越えているのでしょうか。ここでは企業がどのような工夫で環境を改善したのか、3つの成功事例を紹介します。
事例1:業務効率化の起点としてGoogle Workspace導入
製造業A社は、Google Workspaceを段階的なDX推進として導入することで業務効率を改善しました。従来はオンプレミスのメールサーバーを運用しており、メンテナンスの負荷が大きく、ファイル共有も非効率な状況でした。
一人情シス担当者は、小規模なパイロットプロジェクトとして経営層に対して初期投資の少なさとランニングコストの削減効果を数値で示しました。まず経営陣と各部門のキーパーソンから開始し、徐々に全社員に展開。部門別の勉強会を開催し、実際の業務での活用方法を具体的に示しました。
結果として、コラボレーション効率の大幅改善を実現し、作業時間削減を達成。この成功体験がリモートワーク環境の整備につながり、コロナ禍において他社よりもスムーズにリモートワークに移行できました。
事例2:現場主導のRPA導入による業務自動化
サービス業B社では、現場主導でのRPA導入により定型業務の自動化を実現しました。
一人情シス担当者は、月次レポートの作成、定型的なデータ入力、システム間のデータ連携などを自動化対象とし、比較的導入しやすい価格帯のRPAツールを選択。「簡単な定型的な作業」から自動化を開始し、効果を確認しながら徐々に「複雑な業務の自動化」を展開しました。
結果、大幅の作業時間削減を達成し、戦略的業務への時間確保を実現。この取り組みが現場の業務改善意識向上につながり、他の部門でも業務の自動化を提案してくる文化が生まれました。
事例3:外部パートナーとの協力による孤独感の解消
小売業C社は、地域の信頼できるIT企業との関係を築くことで技術的な相談や、IT戦略全般についても議論することで孤独感を解消しました。
C社からは業界動向や具体的な業務課題を共有し、IT企業からは技術的なアドバイスと最新の技術動向を提供してもらうことで、Win-Winの関係を築きました。結果として、精神的負荷が軽減され、技術的サポート体制を確立し、計画的なIT投資が可能になりました。
一人情シスの担当者による環境の改善とは

限られたリソースで幅広い業務を担う一人情シス担当者は、成果を積み重ねながら、いかにして環境を改善すれば良いのでしょうか?。ここでは、社内環境の改善方法から、今後求められるスキルまで、一人情シスが自分らしい成長を実現するための具体的な戦略を紐解いていきます。
社内でのポジション確立と成果の可視化
一人情シスが社内で適切な評価を得て環境を改善するには、自分の貢献を可視化することがおすすめです。中でもコスト削減効果の数値化が効果的でしょう。
たとえば、クラウド移行によるサーバー維持費の削減、業務効率化による工数削減といった具体的な数値で示せます。自動化により月次作業を10時間から2時間に短縮した場合、年間で96時間の工数削減効果を示すことで、その価値を明確に伝えられます。
評価指標では、システム稼働率の向上、ユーザー満足度の測定、プロジェクト完了率・期間短縮率など、「客観的」かつ「測定可能な指標」を設定することが重要です。
組織全体のIT力向上と人材育成
一人情シスの状況を根本的に改善するためには、「組織全体のIT力向上」が重要です。段階的な人材育成アプローチとして、まず「基礎知識の共有」から始めることが良いでしょう。
ITリテラシー向上研修や基本的なトラブル対応方法の教育で、全社員のITスキルの底上げを図ります。簡単な問題は利用者自身で解決できるようになり、一人情シスの負荷軽減につながる可能性が高まります。
次の段階では、各部門でのIT担当者を指名し、業務レベルに応じた責任範囲を設定することをおすすめします。これにより徐々に組織全体でIT業務を分担する体制を構築します。
戦略的スキルアップの方向性
現在の市場動向と将来性を考慮すると、情シス担当者がスキルアップする際、特に注目すべき分野があります。
セキュリティ分野は、需要が高く、将来性も確実な領域の1つといえるでしょう。初級レベルでは情報セキュリティマネジメント試験、中~上級レベルではCISSPやCISAなどの資格取得が視野に入ります。
クラウド分野では、AWS、Azure、GCPの認定資格取得で、市場価値の向上に直結します。
業務改善分野では、RPA、データ分析・BI、プロジェクトマネジメントなどのスキルが求められます。業務プロセスを理解した上でのIT活用提案は今後のIT業務の改善に直結します。
さまざまな分野で基本的なスキルや知見を得て、対応可能なメンバーを育成し、時には外部委託も活用することで組織的に一人情シスの現状を改善することが可能となります。
企業が一人情シスを卒業するために

「一人情シス」体制から脱却し、持続可能なIT運用体制を築くには、企業としての意思決定と具体的なアクションが求められます。
この章では、現状を正しく伝えるための社内資料の作成と企業が認識すべきコストをご紹介します。
説得力のある社内資料の作成
一人情シス状況の改善を経営層に提案する際には、データに基づいた論理的な資料作成が効果的でしょう。
現状分析の数値化として、作業時間を詳細に記録することから始めましょう。作業時間を業務別に集計し、どの業務にどれだけの時間を費やしているかを明確にします。システム障害対応による損失時間の計算も重要です。
費用対効果の明確化の面では、人件費換算で外注費用と対比を示すことが有効でしょう。専門業務を外注した場合のコストと、社内で対応する場合の時間コストを比較し、どちらが経済的に合理的かを示すとよいでしょう。
外注・SaaS活用の説明ロジック
外注やSaaS活用を経営層に提案する際には、コスト比較だけでなく戦略的な価値を示すことが重要です。
この場合、専門人材採用コストとの比較が効果的といえます。IT専門人材の採用には、求人費用、面接コスト、育成期間中の人件費など、隠れたコストが多く存在します。外注費用を比較することで、外注時の経済的合理性を示すことができます。
固定費から変動費への転換という視点も重要です。人件費は固定費として企業の負担となりますが、外注費用は業務量に応じて調整可能な変動費として扱うことができます。
まとめ:孤独だけど、ひとりじゃない

共通する課題と解決への道筋
全国には、あなたと同じように「一人情シス」として多くの課題を抱えながらも、日々業務に向き合っている担当者が数多く存在します。
この状況は決して珍しいものでも、絶望的なものでもありません。
重要なのは、孤立せずに正しいアプローチを見つけ、必要な支援を適切に得ることです。外部リソースや社内の理解を得ながら取り組むことで、限られた環境下でも着実に成果を上げ、環境を改善するきっかけを得られるでしょう。
段階的改善の実践的アプローチ
今すぐ全部を変えることはできない場合、「1つずつ手放す」ことから始めることで、段階的な改善を進めましょう。
<実践的アプローチの例>
Step 1:現状把握
自分の業務時間の詳細な記録から始めます。1週間程度、15分単位で自分の作業内容を記録し、どの業務にどれだけの時間を費やしているかを客観的に把握します。
Step 2:小さな一歩
最も効果が期待できる1つの業務から外注化を検討します。同時に、社内でITに関心の高い1人からIT教育を開始し、将来の協力者を育成します。
Step 3:成功体験の積み重ね
実施した改善の効果を数値で可視化し、経営層への報告と次の改善ステップの提案を行います。小さな成功を積み重ねることで、より大きな改善への理解と支援を得ることができるでしょう。
一人情シスの価値と未来への展望
一人情シスとしての経験は、企業にとって非常に価値の高い資産であり、あなた自身のキャリアにとっても大きな財産です。
限られたリソースでの問題解決能力は、どのような環境でも通用する普遍的なスキルです。経営視点とユーザー視点の両方を理解している人材は、IT業界において非常に貴重な存在となります。
一人情シスは孤独で大変な役割になりがちですが、同時に企業のデジタル化を支える重要な存在です。あなたの経験と努力は、自身のキャリア形成のみではなく会社の成長を支える大きな財産となります。
今日から小さな一歩を踏み出し、より良い一人情シス、そして将来への道筋を築いていきましょう。